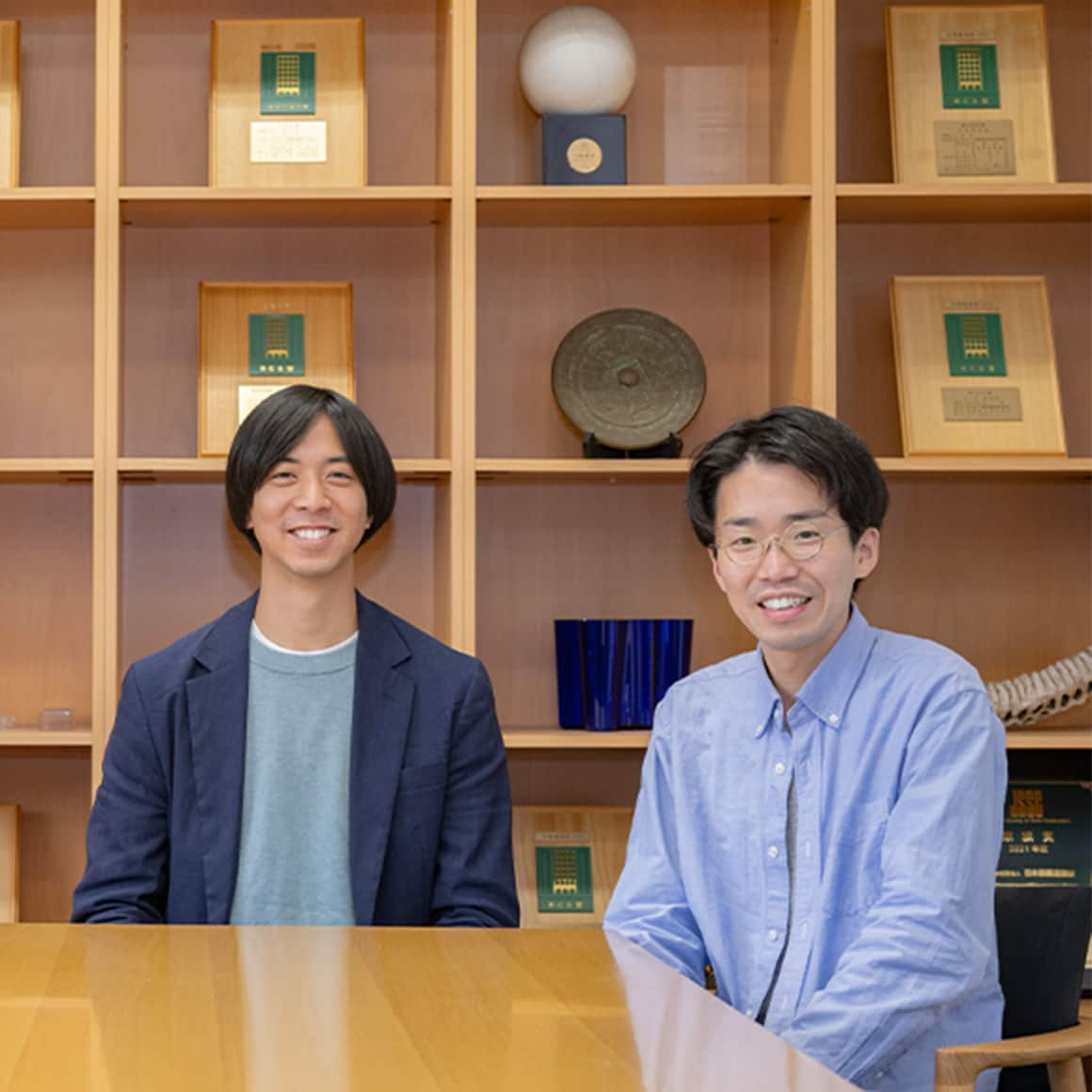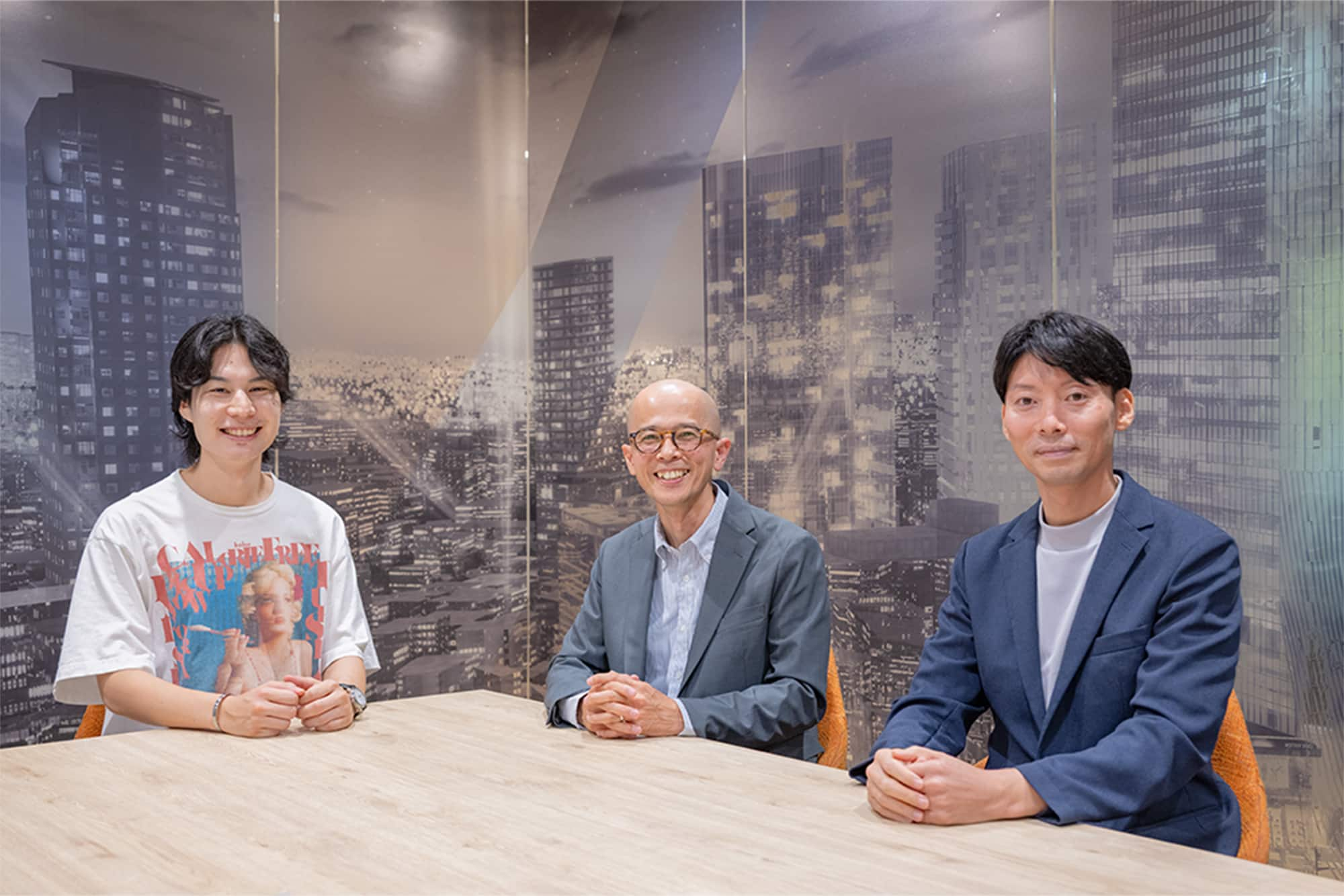index
渋谷のまちの人と来街者を
つなぐ、まちづくりとして
のお祭り
――まずは「渋谷盆踊り」が生まれた経緯について教えてください。
長谷川 きっかけは、東急さんと「渋谷の真ん中で盆踊りをやったら楽しそうだよね」との会話から始まったと聞いています。2016年末に、行政や警察、事業者、商店街などの関係者が協力して初めてカウントダウンイベントを実施するなど、新たなイベントへの機運が高まっていました。
嶋田 当社では、渋谷のまちが抱えるさまざまな課題を克服すると同時に、新しいビジネスの創出やエンタテイメントの集積を目指し、「エンタテイメントシティSHIBUYA」をビジョンに掲げ、渋谷駅周辺の再開発を推進してきました。盆踊りは夏の風物詩として、渋谷のまちの人たちと渋谷に来る人たちが一緒に楽しめる場となる、それを渋谷の真ん中で実現することに魅力を感じました。
長谷川 私は渋谷生まれ渋谷育ちで、家業の傍ら、30代から商店街振興組合とその若手世代による道玄坂青年会にも関わってきました。理事長から「青年会で企画を」と言われたときは、正直「なぜ盆踊り?」と戸惑いました(笑)。聞けば、理事長は子どもの頃に体験した地元の盆踊りの記憶を強く持っていて、それを次世代に体験してもらいたいという想いがあったとか。私自身もずっと交通規制内の道玄坂を活用したイベントに魅力を感じていたこともあり、実行委員長を引き受けることになったのです
まず動いたのが、盆踊りのテーマを決めることでした。青年会の仲間たちで話し合う中で、「ふだん、渋谷のまちの活動をしていても“顔”が見えてこないよね。渋谷に来る人たちとの接点の場を作っていこう」という意見が出たのです。そこで、「渋谷のまちの人と来街者をつなぐ」というテーマが生まれました。
夏の風物詩になるまで
——半年間のゼロからの挑戦
――実際に2017年の開催に向けた準備はどのように進んだのでしょうか。
長谷川 検討を始めたのが1月で、開催は8月。半年でゼロから整える必要がありました。とはいえ、太鼓は誰が叩くのか、櫓はどう建てるのか、最初まったくの手探りでしたね。区内の盆踊りを熟知している区役所の担当者に、踊りをリードしてくれる婦団連さんや、太鼓の叩き手のゑびす太鼓さんをご紹介いただいたり、長く続く大江戸まつり盆踊りにかかわる専門家に相談したりしながら、少しずつ道筋を立てていきました。さらに行政や警察との協議の面で東急さんが力を貸してくださった。商店街は主に地元の合意形成を担当し、住民や商店主、先輩方、運営スタッフらの意見を丁寧に調整しながら、企画を形にしていきました。
岩瀬 渋谷で夜間に道路を交通規制して行う唯一のイベントということもあり、企画運営を担う私たちは「安全に無事終えること」を最優先に据えました。人の流れを管理する人員配置、雨天やトラブル時の中断・再開のシナリオ、交通規制の時間を厳守するための進行管理など、徹底的に安全対策を重ねていきました。協賛集めも課題でしたが、「地域と共に行う都市型盆踊りが多様な層の人々にアプローチできる」ことを訴求するなかで、幅広い企業に賛同いただくことができました。
嶋田 当社としては行政や警察との信頼関係を基盤に、交通規制やリスク対策の調整を進めました。予算管理においては、安全面のコストは十分に検討しました。さらに商店街さんや東急エージェンシーさんとも毎週のように会議を重ね、意見をすり合わせていきました。こうした中で、それぞれの得意分野を活かしながら役割分担する体制が生まれたことが、盆踊りを継続的に開催できている大きな要因だと感じています。
――初回から大きな反響があったそうですね。
長谷川 はい、初回からたくさんの来場者であふれかえりました。当初はたまたま渋谷に来て、盆踊りを楽しまれた方が多かったのですが、年々「渋谷盆踊りを目指して来る」人が増えています。6回目となる今年は台風予報に振り回されながらも無事開催でき、約6万2千人が来場。うち3割は外国人で、国際色豊かな輪が広がりました。浴衣姿の親子連れから観光客まで、世代や国籍を超えて一緒に踊る光景は本当に感動的です。
渋谷の中心で垣根を超えた
人々が輪になる、
非日常の体験
――「渋谷盆踊り」ならではの特色や魅力はどこにあるでしょうか。
長谷川 やはり、SHIBUYA109前というビルに囲まれた異空間で、伝統的な盆踊りを楽しめる点です。曲目は「オリンピック渋谷音頭」「渋谷音頭」「夢みる渋谷音頭」といった渋谷ならではのオリジナルに加え、「東京音頭」「炭坑節」といった幅広い人が知っている定番曲が中心で、渋谷にゆかりのあるゲストによる歌のパフォーマンスも行われます。振り付けは簡単で、飛び入りでもすぐ踊れる。だから、外国人観光客も自然に輪に加われるんです。
嶋田 渋谷には多様な価値観をベースとしたさまざまなニーズに対応する複合的な魅力があります。非日常体験、日本文化の継承、外国人観光客の誘致――それらを一度に体現できるのが渋谷盆踊り。櫓を囲み、老若男女も国籍も関係なく一つの輪になる。この光景が「渋谷らしさ」を象徴していると感じます。
岩瀬 渋谷は人が多いことやハロウィンの混乱でネガティブに語られることもありますが、盆踊りでは「平和でポジティブな渋谷」が体現されています。動画共有SNSでのコメントでも「平和でいい」「こういうイベントこそ渋谷らしい」といった声が多いんです。渋谷のブランド価値を高める意味でも大きな役割を担っていると感じています。
――6回の開催を経て、運営チームにも変化はありましたか。
長谷川 準備は2月から始まり、週に一度は顔を合わせて打ち合わせします。本当に濃い関わりなので、信頼関係が深まり「ここは任せられる」という阿吽の呼吸ができてきたと感じます。
岩瀬 今年は盆踊り終了後の振り返りで、長谷川さんから「今までで一番いいチームだった」と言っていただき、嬉しかったです。互いを信頼して自分の役割に集中できたからこそ、自発的な提案も増え、よりスムーズに動けました。
嶋田 開催を重ねるごとに役割分担が確立されて、メンバーが一人でも欠けると成り立たないと実感しています。調整に苦労が多いこともあいまり、何度見ても本番は圧倒的なシーンに感動します。いつもの渋谷で、非日常な光景が繰り広げられBEGINさん(*)のパフォーマンス中に、多くの参加者が夢中になっている姿を見て、感動で涙が出てしまいました(笑)。
- (*)渋谷を「第二の故郷」と語り、渋谷盆踊りのスペシャルゲストとしてイベントを盛り上げた。
変化に寄り添い、
「盆踊りといえば渋谷」
と愛される存在に
――最後に、「渋谷盆踊り」で描きたい渋谷のまちづくりと未来について教えてください。
長谷川 私の理想は、映画『ニューシネマパラダイス』に出てくる映画館や広場です。人々が自然に集まり、恋人や家族、友人同士が思い思いに楽しむイメージ——「渋谷盆踊り」もそんな空間になれたらと思っています。今後も盆踊りを丁寧に続けて少しずつ大きくしていき、将来的には道玄坂と文化村通りのエリア全体が賑わうようなイベントにすることも構想しています。積み上げた結果として、10年、15年後に「あたたかで楽しい盆踊り」と評価してもらえる、「盆踊りといえば渋谷」と言われる象徴的な存在にしていきたいですね。
岩瀬 渋谷のまちの魅力は、どんな人でも受け入れてくれる器の大きさにあると感じます。個人的にも学生時代からこのまちで過ごし、いまはまちづくりの運営側として関わっている。少しでも恩返しができていると感じると同時に、地域のみなさんのまちへの思いに触れるたび、「もっと良くしたい」と気合いが入ります。いま世界中で分断が語られる中だからこそ、渋谷盆踊りが国籍や性別を超えて人々をつなぐイベントになり、さらにポジティブな渋谷のイメージを広げていけたら嬉しいです。
嶋田 私たちが考える渋谷らしさとは「いつでも誰もが面白いことに、出会い、関わり、挑める」こと。まちの方も、来街者も、働く方々も、まちに関わるすべての方が、毎年渋谷の盆踊りを楽しみに待っていてくれるようなイベントに育ってくれたら嬉しいです。100年に一度と言われる渋谷の再開発に合わせて、今後も渋谷のまちの機能の更新を取り込みながら、多くの人に愛される盆踊りとして進化していくお手伝いをしていきたいです。