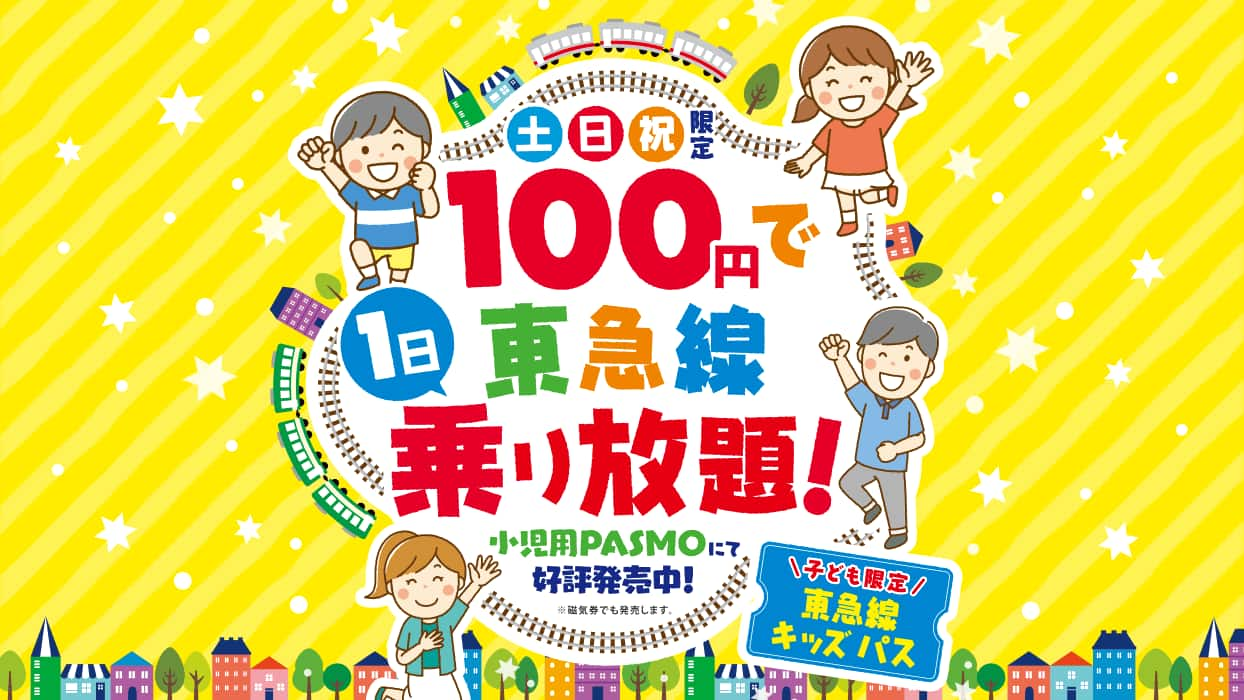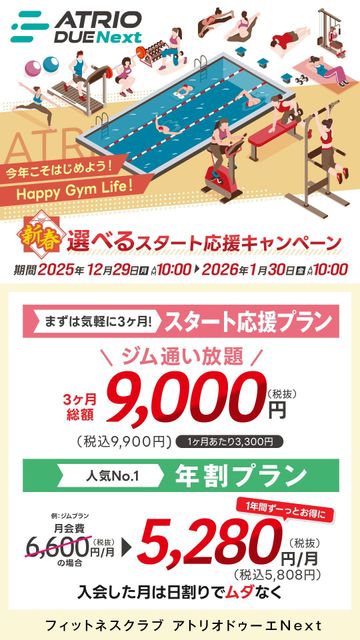今やすっかり秋の風物詩となったハロウィン。カボチャの料理やお菓子を楽しんだり、ちょっぴりホラー要素のある飾り付けをしたり、コスプレやホームパーティーで盛り上がる人も多いでしょう。でも、毎年楽しんでいても、ハロウィンが具体的にいつで、もともと何の日なのかご存じない人もいるのではないでしょうか?
そこで今回はハロウィンの起源や仮装の意味、お菓子を配る理由などについてご紹介します。2025年のハロウィンイベントも紹介しますので、ハロウィンの背景を知って今年のイベントをよりいっそう楽しみましょう!
ハロウィンはいつ?
ハロウィンは毎年「10月31日」に行われる行事です。この日付は年によって変わることはなく、毎年固定されています。したがって、今年のハロウィンは「2025年10月31日(金)」に開催されます。
ハロウィンは「アメリカのお盆のようなもの」と聞いたことがある人がいるかもいれませんが、実はその起源はアメリカではありません。ハロウィンも確かに「先祖が返ってくる日」ではあるのですが、日本のお盆とはちょっと意味合いが違うようです。ハロウィンが10月31日になったのも、実はその起源が関係しています。
次からはハロウィンの起源について紹介します。
ハロウィンの起源は?

現在は世界中で仮装を楽しむ日になっているハロウィンですが、その起源は2000年以上前、アイルランドを中心に古代ヨーロッパ各地に住んでいたケルト人が行う、「サウィン祭(Samhain、サムハイン)」という説が有力です。そこから長い年月をかけ、各国の文化や風習などが結びついて今の形になってきました。
古代ケルトのサウィン祭
ケルトでは、夜を重視し祝日の前夜祭を盛大に祝う風習がありました。ケルト人の暦では、11月1日の日没が元旦(サウィン)とされており、サウィンは元旦と同時に、収穫と狩りの季節が終わって冬が始まる日。そのため、前日の10月31日はサウィン祭として、1年の終わりを盛大に祝いました。祭りにあわせて狩りでつかまえた動物を解体し、祭のあいだはその皮や首を被り儀式を行ったとされています。
サウィン祭は同時に、死者を偲ぶ夜でもありました。異界との境目が曖昧になって、死者の魂が現世に戻ってくる日と信じられていたのです。
ただし、サウィンの日は祖先の霊だけでなく、悪霊も地上にやってきて生者の魂を連れていくとも考えられていました。そこでケルト人はサウィン祭で悪霊を追い払うために火を焚き、収穫物や動物を供物として捧げ、悪霊に生者だと気づかれないように死者の仮装をしたとされています。サウィン祭の火は魔よけのために家に持ち帰り、祖先に感謝して冬を越せるように祈りました。
キリスト教の諸聖人の日
サウィン祭などのケルトの文化は、ケルト人のあいだにキリスト教が広まったことで、少しずつ廃れていきました。しかし、10月31日を祭りとする風習はキリスト教と融合しながら残り、今日のハロウィンへと続いています。
キリスト教(カトリック)では8世紀前半頃、11月1日をすべての聖人を記念する「諸聖人の日(All Hallows Day)」と定めています。その後、宗教改革によって、プロテスタントの国では聖人への崇敬が廃止されましたが、カトリックの国やヨーロッパの一部では、諸聖人の日は死者のために祈る日、精霊を祀る日として存続します。諸聖人の日の前夜はAll Hallows Eveningと呼ばれ、略した表記のAll Hallows E'enから、Halloweenに変化していきました。
アメリカでは、アイルランド系の人々が北アメリカに大量に移住したことで、元々あった農業の伝統と融合し、ハロウィンは広まっていきます。宗教的な意味合いはほとんどなく、多少ホラーの要素がある収穫祭のような民間行事として楽しまれています。
今ではヨーロッパでもハロウィンは一般的な行事になっていますが、ハロウィンはキリスト教の行事ではありません。サウィン祭など異教の行事が起源となっていることもあり、キリスト教徒は参加すべきではないという声もあります。しかし、参加する人は年々増えており、人気のイベントとなっています。
ハロウィンではなぜお菓子を配る?

子供たちが仮装して近所の家を訪れ、「トリック・オア・トリート!(お菓子をくれなきゃ、いたずらするぞ)」と声をかけてお菓子をもらう光景はハロウィンでおなじみですね。この風習は、ヨーロッパで古くから行われた「ソウリング(Souling)」や「ガイジング(Guising)」がもとになっているとされています。
ソウリング(Souling)
「ソウリング」は15世紀以降、アイルランドやイングランドなどで見られる風習です。これらの地域の人々は、諸聖人の日とその翌日の「死者の日」には、貧しい人々が周囲の家を訪れ、死者のために祈る代わりに食べ物などをもらう風習がありました。その後、子供たちがこの慣習を受け継いでいきましたが、その当時は十字架をあしらった「ソウルケーキ」を渡して祈ってもらうことが流行していたそうです。
前述のサウィン祭では、死者になりすますために死者のための供物を受け取る風習があり、その影響もあるのではないかと考えられています。
ガイジング(Guising)
16世紀ごろのスコットランドやアイルランドでは、ソウリングとは別に「ガイジング」と呼ばれる伝統もありました。ガイジングは仮装した人が家々を回り、歌や詩、ダンスなどのパフォーマンスを披露し、見返りに食べ物や小銭をもらうもの。時には家々を回る際に「歓迎しなければいたずらする」と脅すこともありました。現在のハロウィンの要素が見えますね。
ちなみに、「トリック・オア・トリート」の掛け声が最初に使われたのは、1900年代前半のカナダだといわれています。アイルランド系移民の影響で、それ以前も仮装した子供たちによるガイジングの風習はありましたが、掛け声は定まっていなかったようです。それ以降はマスコミなどの影響もあり、1940年頃にはアメリカ・カナダ全土に広まりました。
なお、ハロウィンの起源の地であるヨーロッパでは、1980年代に映画「E.T.」によって認知度が高まるまで、「トリック・オア・トリート」の掛け声は一般的ではありませんでした。
ハロウィンで仮装するのはなぜ?

ハロウィンといえば仮装が定番ですが、もともとは宗教的・精神的な意味合いがあり、古代の風習が現代のスタイルに変化し、今のような仮装文化へと発展していった背景があります。
もともとハロウィンの仮装は「悪霊に生きた人間だと悟られないようにする」ために行われていました。この風習は、古代ケルトのサウィン祭に由来しており、当初は動物の皮や頭を被ったり、悪魔や魔女の仮装をしたりと、悪霊との同化が目的でした。
現代では、仮装そのものを楽しむ傾向が強くなっています。今でも悪魔や魔女といったホラー要素のある仮装はハロウィンの定番ですが、それに限らず映画やアニメのキャラクター、特定の職業の制服など、さまざまなコスチュームが楽しまれるようになりました。特に、コスプレ文化になじみのある日本では、「悪霊から身を隠す」という範囲を超え、独自の発展を遂げています。
ハロウィンとカボチャの関係

ハロウィンの象徴ともいえる「カボチャのランタン」、通称「ジャック・オー・ランタン」には、アイルランドの民話にもとづく由来があります。もともとはカボチャではなく、別の野菜が使われていたことをご存じでしょうか?
野菜を使ったランタンは、ケルトのサウィン祭がもとになっています。ケルトのサウィン祭では、悪霊を追い払うため、カブやジャガイモといった収穫したばかりの野菜に恐ろしい顔を彫る文化がありました。これには実用的な目的もあり、金属製のランタンは高価だったため、顔を彫った野菜をランタンとして使ったといいます。
ジャック・オー・ランタンは、アイルランドに伝わる民話の登場人物「ジャック」という男の話がもとだとされています。嘘つきでずる賢いジャックは悪事をはたらいて、死後に天国からも地獄からも受け入れを拒否されてしまいます。天国と地獄のあいだの暗闇を永遠にさまようジャックに、情けをかけた悪魔が手渡したのが、地獄の火を入れた「カブのランタン」でした。これがジャック・オー・ランタンの起源とされています。
アイルランドやスコットランドでは、ハロウィンにカブのランタンが使われていますが、アメリカではカブがあまり一般的でなかったため、より手に入りやすく加工しやすい「カボチャ」が使われるようになりました。現在では「ハロウィンといえばカボチャ」というイメージが強くなっています。
魔除けのための恐ろしい顔を彫った野菜と民話、地域の事情が重なって、現在のようなカボチャのランタンの文化が生まれたのですね。
日本にハロウィンがやってきたのはいつ?
今では日本でもすっかりおなじみとなったハロウィンですが、その歴史は意外にも浅いもの。始めは1970年代に、東京・原宿の雑貨店「キディランド原宿店」で、ハロウィングッズの販売に力を入れるようになったことがきっかけでした。1983年には販促企画として一般参加が可能なハロウィンパレードを開催。これが日本初のハロウィンパレードだとされています。当時はハロウィン自体の知名度が低かったため、参加者の多くが外国人だったそうです。
日本でハロウィン文化が一気に浸透するきっかけとなったのが、1990年代後半に「東京ディズニーランド(R)」が開催したハロウィンイベントです。特に「ディズニー・ハッピー・ハロウィン」の仮装イベントは話題を呼び、家族連れや若者を中心に大人気となりました。同年に神奈川県川崎市で仮装パレード「カワサキ ハロウィン」が開催されたこともあり、このとき「ハロウィン=仮装イベント」というイメージが定着したとされています。
2025年のハロウィンイベント
【二子玉川・10/25〜26】二子玉川ハロウィンパーティー2025

二子玉川ライズ・ショッピングセンター、二子玉川ライズ・ドッグウッドプラザ、玉川髙島屋S.C.は、三施設による合同イベントとして、親子で楽しめる企画を開催!不思議な世界を旅することができるスタンプラリーを中心に、ワークショップやエアー遊具など体験型アクティビティが満載!さらに今年は、ステージをディスコ風にアレンジした「ハロウィンキッズディスコ」が登場します!
・開催期間:2025年10月25日(土)、26日(日)10:00~17:00
・場所:二子玉川ライズ ガレリア、中央広場、ハナミズキ広場、二子玉川ライズ スタジオ & ホール、⽟川髙島屋S.C.南館1Fプラザ(正面入口)
【青葉台・10/25〜26】HAPPY NEW HALLOWEEN

青葉台東急スクエアの新たな魔法で遊ぼう!今年のハロウィンは、ドレスやティアラで「おひめさま/王子さま」に変身したり、「おもしろ早口ことば」にチャレンジしながら館内を巡るスタンプラリーを開催します!26日(日)はハロウィーンクリーンウォークも同時開催!!青葉台東急スクエアで楽しいハロウィンを過ごそう♪
<なりきり!おひめさま・王子さまになろう!おひめさまごっこプロジェクト(R)>
・開催期間:2025年10月25日(土)~10月26日(日)
・開催時間:11:00~15:30(ドレス貸出13:30まで)
・開催場所:South-1 本館 1F アトリウム
※お買い上げ条件あり、当日10時~会場にて整理券配布
<ハロウィン早口スタンプラリー>
・開催期間:2025年10月25日(土)~10月26日(日)
・開催時間:11:00~20:00
・スタンプラリー用紙配布場所:South-1 本館 1F アトリウム
<青葉台ハロウィーンクリーンウォーク>
・開催期間:2025年10月26日(日)
・開催時間:12:00~13:00
・開催場所:South-1 本館 1F アトリウム
【たまプラーザ テラス・10/11-12】シャカシャカ!ハロウィンキーホルダーづくり

民間学童の東急キッズベースキャンプαたまプラーザです!普段は小学生が放課後過ごす場所ですが、たまプラーザテラス15周年という事で未就学のお子様向けにワークショップを開催いたします♪
・会場:たまプラーザ テラス ゲートプラザ 2階 セカンドコート
・参加条件:未就学児(3歳から6歳)対象
・参加費:無料
・定員:各回先着50名(整理券配布なし)
・時間:第1部10:00~12:00 第2部13:00~15:00
【たまプラーザ テラス・10/19】クリエイターズハロウィンマーケット

クリエイターが制作した作品を直接見て触れて楽しむことができる「クリエイターズマーケット(てづくり市)」を開催します!今回のテーマは『ハロウィン』。ハンドメイドアクセサリーや布小物をはじめ、インテリア雑貨やフラワーアイテムなど、幅広いジャンルが勢ぞろいします。さらに、キッズ向けのアクセサリーや小物もご用意しておりますので、ご家族でハロウィンアイテムを身にまといながら、特別な一日をお楽しみください♪
・会場:たまプラーザテラス ゲートプラザ 1階 ステーションコート ※荒天中止
【たまプラーザ テラス・10/18〜19】オリジナルハロウィンリースを作ろう

GAPの折り紙や画用紙を使ってオリジナルハロウィンリースを作ろう!!折り紙を折ったり、シールを貼ってオリジナルのハロウィンリースをGAPのスタッフと一緒に制作します。
・会場:たまプラーザ テラス ゲートプラザ 1階 モールA口
・参加条件:保護者の同伴が可能なお子様(目安~12才)
・定員数:各回12名(開始30分前に整理券配布)
・参加費:無料
・時間:14:00~ 14:30~ 15:00~ 15:30~
・問い合わせ先:ギャップ/ギャップキッズ たまプラーザ テラス店 045-905-0721
【たまプラーザ テラス・10/25〜26】オリジナルハロウィンBOXを作ろう

ドリンクパックを再利用してジャックオーランタンのお菓子BOXをGAPスタッフと一緒に作ろう!
・会場:たまプラーザ テラス ゲートプラザ 1階 モールA口
・参加条件:保護者の同伴が可能なお子様(目安~12才)
・定員数:各回9名(開始30分前に整理券配布)
・参加費:無料
・時間:14:00~ 14:30~ 15:00~ 15:30~
・問い合わせ先:ギャップ/ギャップキッズ たまプラーザ テラス店 045-905-0721
歴史や由来を知ってハロウィンを楽しもう
ハロウィンは、毎年10月31日に行われる秋の恒例イベントです。もともとは古代ケルトの祭でしたが、長い年月をかけて、現代のハロウィンの形へと発展していきました。
ハロウィンの歴史や意味を知ることで、単なるイベント以上の深みや面白さを感じられるはずです。今年のハロウィンも、その背景に想いを馳せながら楽しんでみてはいかがでしょうか?
掲載店舗・施設・イベント・価格などの情報は記事公開時点のものです。定休日や営業時間などは予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。