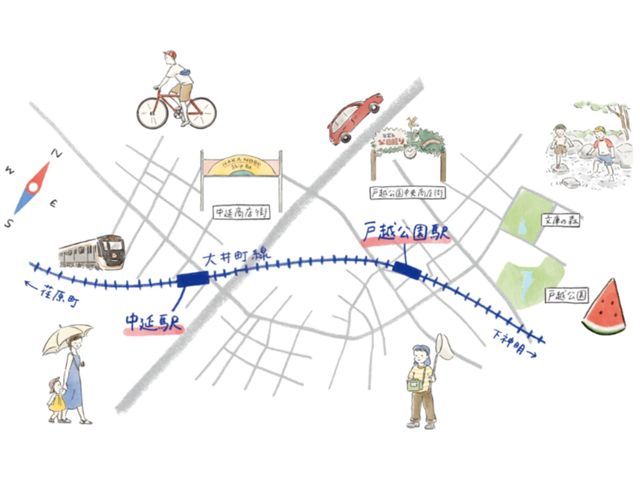東急線沿線の駅にまつわる人やお店、エピソードを、東急線沿線にゆかりのある方々にエッセイ形式で執筆いただく本企画「あの駅で降りたら」。
今回は、エッセイストの中前結花さんが、目黒駅をテーマにエッセイを執筆。就職を機に上京し、慌ただしく過ぎ去る日々の中での、運命的な出会い。そして憧れだった目黒での思い出。
目黒を舞台にした、まるで映画のワンシーンのような日を綴ったエッセイをお楽しみください。
中前結花
兵庫県生まれ。エッセイスト。2010年に上京。会社員を経て独立し、現在は多数のWebメディアで執筆中。2023年には初の単著エッセイ集『好きよ、トウモロコシ。』(hayaoki books)、2025年9月には『ミシンは触らないの』(hayaoki books)を刊行。以降も新刊を控える。目標は、強くてやさしい文章を書くこと。
X:https://x.com/merumae_yuka
--
恋人ができなかった。
ずっとずっとできなかった。もう10年以上も前の話だ。
「若い人は恋愛を謳歌するもの」という風潮が、今よりうんとうんと色濃かったとき。
それでも、わたしにはできなかった。
上京さえすれば、東京という街に飛び出しさえすれば。きらきらとした素敵な出会いがたくさん待ち受けていると思っていたのに、わたしのもとへはそんな機会がちっとも訪れなかったのだ。
22歳の春。最寄り駅のロータリーで咲きこぼれる桜に見送られながら兵庫県の片田舎をあとにし、上京してきた。
けれどもその新幹線に乗り込むとき、見送りに来てくれた何人もの友に泣きながら手を振っているときも、わたしの隣には母がいた。「どうしても引っ越しを手伝ってほしい」とねだったからである。
母はペットボトルのお茶で指先を温めながら、涙を拭うわたしを隣でじっと見ていて、新幹線のドアが閉まってスーッと走り出したとき、
「また会えるよ。これで終わりじゃないねんから大丈夫大丈夫」
そう言って、ドアの前で抱きしめてくれた。わたしは今でもこのときのことを、よく思い出す。なんだか、わたしの人生のなかでもとりわけドラマチックなシーンであったから。
それにこのときは「青春とは学生時代だけのことだ」と勘違いしていたし、これがそのクライマックスのようにさえ感じていたのだろうと思う。
そしてさらにドラマチックな気持ちを高ぶらせたのは、そのとき父から届いたメールであった。
「東京に行ったらひとり。家事も食事も気をつけて仕事も頑張るように。でも、どうしても辛かったら帰ってきたらいい。待ってるから。もし、そっちでいい男が見つかったらそれはそれで良し。紹介するように。頑張れ」
東京に発つ娘を見送りにくることもしない父だった。それでも普段は言わないことを、ちょっと気張って文面にしてくれたのだと思うと、なんだかたまらなかった。
そんな思いで、わたしは東京へとやって来たのだった。

けれども、その「いい男」というのはいつまで経っても現れなかった。
もちろん仕事を頑張るつもりで、誰ひとり知り合いのいない東京に出てきた。それは間違いないのだけれど、父のメールを読んでからというもの「そうだよなあ」という気持ちもちょっとばかり芽生えていたわたしだった。きっとこの先、東京で恋人を作ることになるだろう。もしかしたら、一生を共にする伴侶だって……なあんてことまで考える。それに東京だもの。「恋愛だってきっと片田舎とはちがう、ぴかぴか輝いたものができるだろう」。なんとなくそんな楽観的で甘い予感を、わたしはその頃、胸の片隅に抱えていたのだった。
しかしながら、恋人はできなかった。
待てど暮らせど、できなかった。2年が経っても、3年が経っても。
言い訳をするならば、あまりにも仕事に夢中になり過ぎていた……といったところはあったかもしれない。おもしろくて、おもしろくて仕方なかった。身の丈に合わないような、ずいぶん立派な役職ももらえて、わたしはとにかく仕事に夢中だったのだ。それ以外のことは、なんにも知らない、中身は大学生のわたしのまま、家では食パンばかりをかじって東京での日々が瞬く間に過ぎていった。

けれども「こういう機会というのは急に巡ってくるものなのだなあ」と、わたしは今になっても思う。とても「ありきたり」な。とても「ありがち」な出会いだった。
大学時代の友に「来てえや」と誘われた飲み会に、知らない男性が3人来ていて、それはつまり「出会いの場」「合コン」というやつだった。
その中に、調子よく冗談をたくさん言ってくれる話し上手の男性がいて、わたしと友はずっと笑ってばかりいた。少し歳上ということもあるかもしれない。なんだかとても喜ばせるのに慣れていて(それでも決して下品でなかった)、可笑しくて可笑しくて仕方ない。大いに会は盛り上がり、なんだか新しいものと出会ったような、とてもたのしい夜だった。
しかしそんな中、不思議とわたしは自分の目の前に座っていた、口数の多くない伏し目がちな男性のことばかりを見ていた。髪の短い、目元のキリッとした、なんだか朴訥(ぼくとつ)とした感じのする人であった。けれども昔はDJをしていて、その場の人々を大きくうねらせていたと言うから、人は見た目ではわからない。
「ありがち」なことであるようにも思った。「話し上手な人より、口数の少ない人が気になりました」というのは。だけど、仕方なかった。わたしはなぜかそのDJの所作ばかりをずっと見ていたのだ。
そして会もお開きになり、みんなで連絡先を交換することになる。
ただ、そのDJだけは少しくぐもった声で、メッセージアプリではなく
「メールアドレスにしませんか?」
と言ってきた。「なんでやろう?」よくわからないけれども、わたしたちはお互いのメールアドレスを交換し合った。
するとその晩、その人から「ぼくは、こういうものが好きです」とえらく長文のメールが届いたのだ。好きな本に、好きな映画、好きな音楽、好きな歴史上の人物……。無知なわたしは「岡田以蔵」のことをたくさん検索しなければいけなかった。
そして、文面の最後に
「話下手なので、自分を上手くアピールすることができなかった、と思ったのです」
とあった。つまり長い長い文章で、その人はわたしにアピールをしてくれたのだ。それは、マッチかなにかの火でも付いたように、わたしには胸がふっと熱くなる出来事であった。
そしてその日を境に、わたしたちは毎日1通ずつ長い長いメールをやり取りすることになる。
内容は、やっぱり「好きな本」「好きな映画」「好きな音楽」について。わたしは「宇多田ヒカルの歌詞が好きです」「松任谷由実を聴いたあとの心地が好きです」「奥田英朗をよく読みます」といったようなことをよく送っていた。
特に「あの曲のあの部分がいい」だとか「この歌詞に胸がぎゅっとなる」だとか。おおよそ、そんなことばかりを送っていたように思う。ふたりとも「言葉」について話すのがすごく好きだった。
仕事は相変わらず忙しかったけれど「家に帰れば、今日届いたメールが読める」。それが、いつしかわたしの毎日のささやかな喜びになっていった。帰り道のコンビニでは、もうそわそわする。朝食のパンを買うときでさえ、なんだか鼻歌を歌っていたい気分だった。

そしてそんな月日が2ヶ月以上続き、ようやく「会ってお話しませんか?」ということになった。なんだかとてものんびりとしたお誘いだけれども、そんなところもその人らしいなと好感を持った。つまりその頃には、もうほとんど好きになっていたのだと思う。
「どこに行きたいですか?」
とたずねられた。わたしはその頃、本当に仕事以外のことに無頓着であったから、自分の最寄りの駅と会社のある原宿、渋谷、家財道具をそろえた池袋ぐらいしか知らなかった。
「お恥ずかしいんですが、わたし目黒とか自由が丘とか、そういうところに一度行ってみたいんです」
そう返事する。聞いたことのあるおしゃれな場所を言ってみた、ただそれだけだった。それに当時、『最高の離婚』(フジテレビ)というドラマを気に入って見ていたために、その舞台となっていた「目黒川沿い」というものを、ちょっと歩いてみたかったのだ。
「それなら、中目黒の方がイメージに近いのかもしれないけれど、川沿いを散策するなら目黒のほうがいいかもしれません。目黒をいっしょに歩きましょうか」
彼はそう言ってくれた。気になる人と目黒川沿いを歩く。そう考えるだけでわたしの胸はどれだけ高鳴ったか。洋服は新宿に出かけて、クリーム色のワンピースを新調した。その日がたのしみでたのしみで仕方なかった。

そしてその日。目黒駅に着いて久々に顔を合わせた。なんと言えばいいかわからなくて、
「ごめんなさい、待ってくれましたか?」
とたずねると、
「まったく。同時に来ました」
そう彼が言ったのが可笑しかった。はじめて訪れる目黒駅。きょろきょろしているわたしに
「行きましょうか」
と言って彼は歩きはじめた。しばらく彼に促されるまま進み、急な勾配の坂を下っていく。気張ってヒールを履いてきたわたしに、彼は
「平気ですか?」
と言ってくれる。わたしはこの、東京の男性がよく言う「平気?」とか「平気ですか?」という言葉がすごく好きだった。関西にいた頃には聞いたことのない言葉だったから。なんだか些細なことでも気遣ってくれているようで、わたしはそれがすごく嬉しかったものだから、「この人も言うんや」と胸が弾んだ。
坂を下り終えてしばらく歩くと橋が見えてくる。ひらがなで「たいこばし」と書いてあった。
「ここから、川沿いに歩きましょうか」
そう提案してもらい、わたしたちはなんでもない川沿いの緑道を歩いた。

本当になんでもない道。ただ青緑に水面が光り、5月の陽を浴びて緑がきれいで。ミスチルの歌詞にある「緑道の木漏れ日」という言葉を思い出して、
「わたしはいま、はじめて本物の緑道の木漏れ日の中にいるんやなあ」
と、そう思った。なんだか胸が浮き立つようで。それでもすごくすごく不思議で。数ヶ月前まで知らなかった人と、こうして「緑道の木漏れ日」を「目黒川沿い」をただ何気なく、おじいちゃんとおばあちゃんのように、ゆったり穏やかにしあわせな気持ちで歩いている。あまり話し上手な人ではなかったから、特にたくさん話すことはしなかった。けれども、本当に嬉しい川歩きだった。

そうして充分に歩いたあと、
「目黒川はたのしめましたか?」
と彼は聞く。
「普通だけど、のどかでいい川でした。たのしかったです」
そう答えて頷くと、彼も頷く。「それじゃあ、喉でも潤そう」と適当なお店を探すことになったのだけれど、週末のカフェはどこもいっぱいだった。少し歩いて「弘南堂書店」という古本屋をふらりと覗いてから、わたしたちは「イトーヤコーヒーショップ」という喫茶店を見つけた。おそらく老舗なのだろう、レトロな雰囲気があって腹の底から落ち着ける良いお店だった。コーヒーを飲みながら、
「いつもメール、たのしみにしています」
「こちらこそ」
やっぱりくぐもった声でぼそぼそと話す。そして、そんな話をひと通り終えると彼は、
「だけど、すごくお仕事が忙しそうですね、心配なほど」
そう言って眉をひそめた。けれどその頃、会社ではとても大きな組織変更があり、わたしが仕切っていた部署は整理(解体)されてしまって、本当は急に「これまでの忙しさ」はどこかへ吹き飛んでいってしまっていたのだった。次の身の振り方を考えなければいけない、そんな状態にあったのだ。
「頑張ったんですけど、精一杯……」
そこまで話すと、なんだかウッと喉がつかえるようになった。いけないいけない。
「慣れなかったけど。わたしなりにやってみたんですけど。だめでした」
そう言って口角をきゅっと無理に上げて笑ってみる。けれど、わたしは目黒のコーヒーショップの窓ガラスの横で。会って2度目の人の前で。もしかしたら恋に落ちているかもしれない人の前で、涙を流してしまった。どうしても堪えられなくて、本当に本当に情けなかった。
大好きな仕事が思うようにいかなくなり、胸に抱えているものがいっぱいあった。それが抑えきれなくて、頬を涙がタラタラと流れて、本当に本当に弱ってしまったのだ。
けれども彼は、慌てることも急にやさしくすることもなく、ただ淡々と、
「見ている人は見てくれていますし、涙は勝手に出てくるものだからしょうがないんです」
と言ってくれた。わたしはおしぼりで頬を拭く。化粧も崩れてぐずぐずで、ああ、鼻水だって出てくる。
「ぼくは、仕事をお金を得るためにやっている『仕方のないもの』だと思って生きてきました。やり過ごしている……みたいな。だから今、すごく新鮮に思って聞いているんです、その必死さを」
そんなふうに話し、それぞれの仕事や、やっぱり好きな本や音楽について話したあと、彼に「出ましょうか」と促され、わたしたちはまた目黒の駅へと戻った。本当に昼間だけの。お昼だけのささやかなデートだった。だけれど、それでよかった。目黒川を見れてよかった。泣いてしまったのが、この人の前でよかった。

そして改札口で、
「新鮮な気持ちにさせてもらって嬉しかったです。目黒川も久々に見れたし。ありがとうございました」
そう言ってもらい、お互いにお辞儀をしてわたしたちは別れた。東京でのはじめてのデート。正真正銘、この目黒川がわたしの東京での初デートだ。それが夕暮れとともに目黒駅で静かに終わったのだった。
けれども、そのあとすぐに。電車が来るまでのほんの短い時間に、彼からまたメールがあった。ただ、いつもの長文ではない。
「今日はありがとうございました。涙を流されたとき、もっと本当は言ってあげたい言葉もあったのですが、言えませんでした。今度、もし今度また目黒川沿いを一緒に歩いてくれるようだったら、手とか、つないでもいいでしょうか」
それだけが書かれてあった。
わたしの胸に、この胸に、吹き荒れるものはなんなのか。思わずホームでうずくまりたくなる、そんな瞬間だった。男性にそんなことなど言われたのは、本当にはじめてのことだったのだ。胸が、どくどくとただ騒いでいた。うるさいほど騒いでいた。
そしてそんなとき、なぜかいちばんに思い浮かべたのは父からのメールだった。
お父さん、お父さんの言っていたような。そういう人に巡り逢えたかもしれへん。
そして、上京のあの瞬間が青春のクライマックスなんかじゃなかったのだ。まだまだ、みずみずしい日々は続いていくのだ、そんなことがはじめてわかった。今日はじめてわかった。

それから2度ほど食事をして、2週間後、わたしたちはまた同じように目黒川沿いを歩いた。
2週間前と変わらず静かでのどかな川だった。緑を見ては、また頭の中ではミスチルの「緑道の木漏れ日」を思い出す。「ああ、この前とやっぱり同じだ」「全部同じだ」「目黒はこういう場所なんだ」わたしは思った。のんびりと穏やかな川沿い。変わったのは、わたしたちの左手と右手だけだった。
--
文/中前結花
写真/Ban Yutaka
編集/菱山恵巳子(ヒャクマンボルト)
掲載店舗・施設・イベント・価格などの情報は記事公開時点のものです。定休日や営業時間などは予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。
Urban Story Lab.
まちのいいところって、正面からだと見えづらかったりする。だから、ちょっとだけナナメ視点がいい。ワクワクや発見に満ちた、東急線沿線の“まちのストーリー”を紡ぎます。