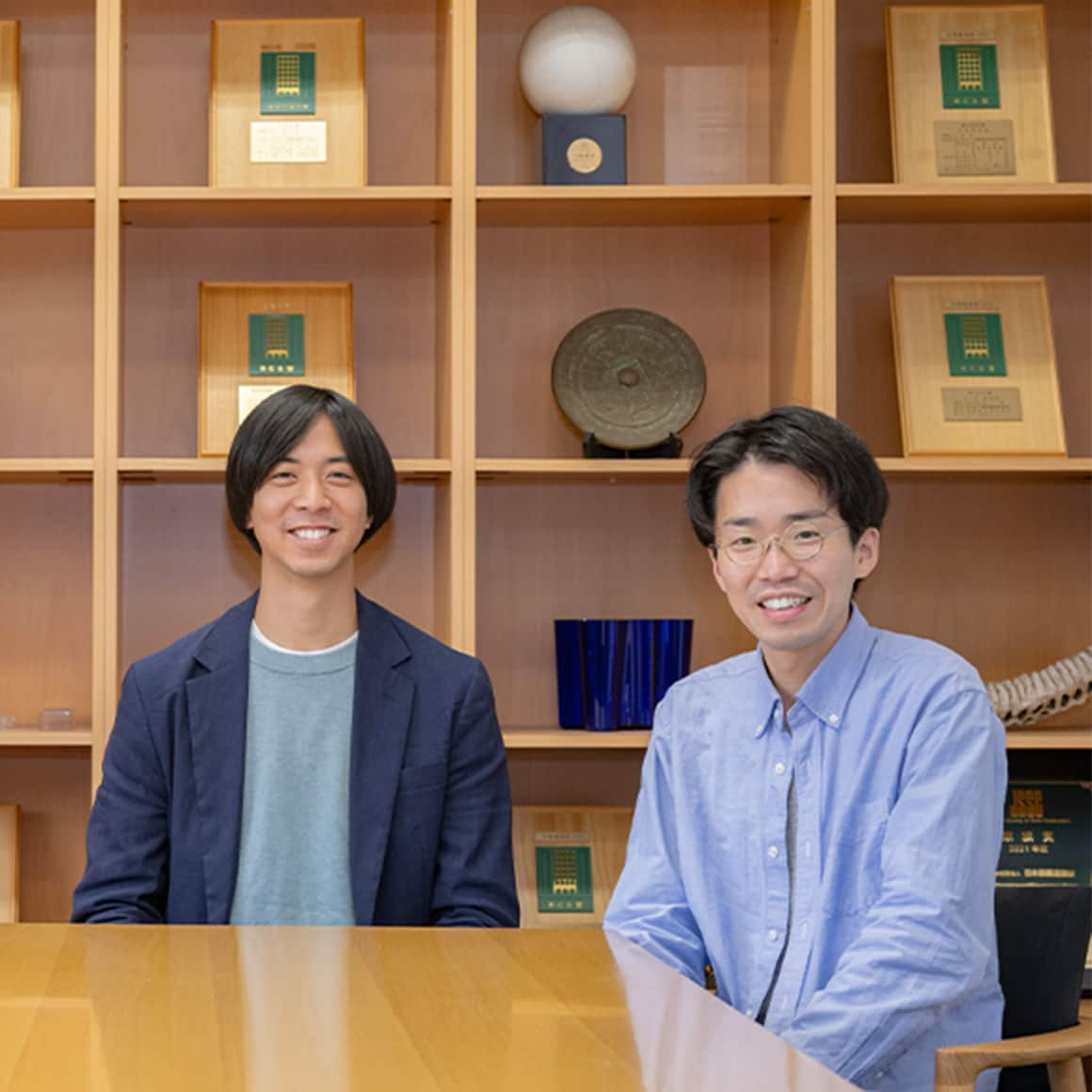渋谷駅街区計画は、「100年に一度」と目される大規模再開発です。2025年5月からは渋谷スクランブルスクエア第Ⅱ期(中央棟・西棟)の工事が始まりました。2010年頃からスタートし、2030年に渋谷駅を中心とした歩行者ネットワークの概成、2031年度には渋谷スクランブルスクエア第Ⅱ期(中央棟・西棟)の完成を予定している遠大な計画を通じ、東急は渋谷に何をもたらそうとしているのか――開発実務に従事している社員たちが語ります。
index
人やモノを動かしながら街を進化させていく。
それが渋谷駅街区最大の特徴
――本プロジェクトが、他の開発と大きく異なる点は何でしょう?
石田 みなさまご存じのとおり、渋谷駅は複数の鉄道路線が接続しているうえに大規模なバスターミナルを擁した都内屈指の交通結節点です。
ご利用者様の多さに最大限配慮し、街の機能を停止させずに開発を続けている点が、本プロジェクトの大きな特徴だと思います。例えば、副都心線と東横線の相互直通運転の際も、鉄道の運行を維持しながら工事を進めていました。その後の駅前広場の区画整理を進めていくうえでも、バス・タクシーなどの交通事業者や鉄道事業者、行政、地元といった多くの関係者と幾度も協議を重ねて合意形成し、人の動きや流れを止めない手法を取っています。
また、かつては渋谷マークシティから東急百貨店東横店のなかを通って銀座線にアクセスできましたが、東急百貨店の解体にともない、私たちは仮設で動線を確保しました。工事期間中、別ルートを移動していただくという選択肢もありましたが、ご利用者様にとっての利便性を優先した結果です。都市機能を高いレベルで維持しながら開発を進めるという手法は、他ではなかなか見られないと思います。
榎本 通常の開発では、土地に占める建築物の割合は、敷地面積より小さくなるよう計画されるものです。しかし、渋谷駅街区ではこれが逆転しています。谷状地形の底に位置する渋谷駅街区では、駅西側の道玄坂上から東側の宮益坂上までをほぼフラットに結ぶネットワーク創出が計画に盛り込まれています。
方法として、敷地外の道路上に歩行者デッキをつくって駅の東西やその間にある複数の建物をつなぐため、敷地面積より建築面積が広くなっているのです。建築物を敷地外の道路上にも張り出させることや、他の建物と接続させることが前提になった計画というのは、かなりレアだと思いますね。
そして、人や自動車の往来におよぼす影響を最小限に抑えるため、道路上の工事は深夜帯などに限定しています。私たちがつくるのは営利目的の商業施設ではなく、人々の鉄道の乗り換えや街から街への移動など公益に資するネットワーク。それでもコストや手間の増大を辞さずに臨んでいるのは、石田が指摘したとおりで、開発の途中経過でも渋谷の機能を維持し続けることが重要だと考えているからです。
既存の計画や慣例に拘泥せず、
展望施設や防災施設などの新たな価値を付加
渋谷スクランブルスクエア SHIBUYA SKY CLOUD HAMMOCK
渋⾕駅東⼝雨水貯留施設:渋谷駅街区土地区画整理事業共同施行者提供
――計画を通じて新たに付加できたと思う「価値」の具体例をご紹介願います
榎本 すぐ頭に浮かぶのは、渋谷スクランブルスクエア東棟屋上の展望施設「渋谷スカイ」です。実は、展望施設は当初の計画に含まれていませんでした。実施設計が終わり、工事着手に向かっているタイミングで、「せっかく渋谷のど真ん中に超高層ビルをつくるのに、限られた人しか最上部に行けないってどうなの?」という意見が出てきまして。
そもそも、足元に無数の人や電車、自動車が行き交うようなビルの屋上全体に、オープンエアの展望施設をつくるというアイデア自体が無謀です。スマホひとつ落下させただけでも重大な事故につながりかねませんからね。建築計画的にもビルの屋上はもともと設備置場でしたので、それの移転先を見つけなればなりませんでしたし、お客様を屋上にあげるエレベーターなどの縦動線を追加する必要がありました。また、主要な収入源であるオフィスフロアの一部を潰して展望施設を作るわけですから、ビジネスの観点からも様々な意見が上がったのも事実です。完成後も運営コストを要する施設になるわけですし。
こんな話を、既に実施設計を終えたタイミングで真剣に検討しはじめたわけですから、最初はみんな半信半疑でした。業界的にも前代未聞な挑戦だと思いますし。それでも計画変更に踏み切ったのは、関係者の間で、渋谷に新たな価値や魅力を付加しなければという強い使命感があったからだと思います。
施設計画担当としては、微細なリスクまで視野に入れた安全対策や、少しでも経済合理性を高める工夫などが求められました。時間的制約があるなかで具体的な形に落とし込むのに大変な苦労を味わいましたよ。しかし、開業後の盛況ぶりを目の当たりにして、苦心した意味があったと思いましたね。渋谷スクランブルスクエアの屋上を「ビルの設備を詰め込んだだけのメンテナンス空間」から「渋谷の一番高いところから街のエネルギーを全身で感じられる空間」へと昇華できたわけですから。やっぱり渋谷のど真ん中で、寝っ転がって空を見られる空間があるって最高だと思います。
石田 私は、広場と防災施設の創出を挙げたいですね。本プロジェクトでは、地上の広場をどんどん拡張する方向で計画変更してきていますし、駅の東西それぞれには地下広場を設け、地上3階の上空部分にも広場を生み出すことになっています。豊富な広場空間の創出は、単に従前の課題だったスペース不足を補うだけにとどまらず、さらなる賑わいの創出、ひいては渋谷の価値向上につながるでしょう。また、駅東側には、集中豪雨などに備えて雨水を一時的に貯めておく地下貯留槽を整備しました。
防災施設の整備は、公共性の高さから行政が担うことが一般的なので、社外の方には珍しく映ったようで、「なぜ東急さんがそこまでやるの?」と質問されることがあるんです。しかし、渋谷駅街区には東横線や田園都市線が停車する地下駅がありますし、私たちは複数の地下広場創出に向けて動いています。近年の自然災害激甚化を踏まえ、渋谷の街に安全性を加味することも開発と一体で行っていくという感覚なのです。
鉄道事業者としての経験や渋谷に注ぐ熱情が、
開発事業をスムーズに牽引
――実務を通じ、どんなところに「東急らしさ」を感じますか?
石田 分社化によって現在の担当事業領域は変わりましたが、弊社には、もともと鉄道事業者というバックボーンがあります。そして、事業パートナーであるJR東日本さんや東京メトロさんはいずれも鉄道事業者です。先に触れた「都市機能を止めない」という点にも通じますが、パートナーにとっての重要な関心事を押さえて臨めるのは私たちの強みだと思いますね。
自社の事業だけでなく各パートナーさんの事業や工事の内容も深く理解し、相手が優先したいであろう点を熟慮したうえで提案を持ちかけています。例えば、安直に運行休止を求めるのではなく、休止を避ける重要性を踏まえて提案できたのも、私たちに鉄道事業者の視点が備わっていたからです。共同事業者さんの事情に配慮できる東急だから、計画全体を円滑に牽引できている側面があると感じています。
榎本 渋谷区との強固な信頼関係のもとで開発を進められている点も、東急ならではだと思います。一般的な開発プロジェクトにおいて、デベロッパーは「申請する側」で、行政は「許可する側」です。しかし、渋谷駅街区における渋谷区と私たちは、協調・連携し合うパートナーという色合いが強い。
一例が、これまで渋谷駅周辺で開発してきた各ビルのデザインです。渋谷区や学識の先生方、地元代表の方々を中心とする渋谷駅中心地区デザイン会議を通じて「同じようなビルが何棟も林立するのは渋谷らしくない」となり、開発プロジェクトによって異なるデザイナーを起用するという大方針がまとまりました。結果、各ビルが個性を発揮すると同時に、ある部分では他のビルとの共通点や一体感も感じさせる絶妙なバランスを実現できているわけです。「お伺いを立てる」「許可する」という一方通行の関係性ではなく、双方向で一緒に新たなモノや価値の創出を目指している背景には、私たちの渋谷に対する愛情や熱意を、渋谷区や関係者の皆様に認知していただけているからだと思います。
目先にとらわれない「渋谷のために」という姿勢が、
結果的に東急を成長させる
渋谷スクランブルスクエア スクランブル交差点からの鳥瞰イメージ(渋谷駅街区共同ビル事業者)
――世の中の変遷速度が加速するなか、今後の対応についてはどう考えていますか?
石田 もちろん、柔軟に対応すべき場面は幾度も出てくるでしょう。例えば、将来タクシープールを地下に整備する計画がありますが、プロジェクトの始動当初は、タクシーを利用する際には乗り場に並ぶのが一般的でした。しかし、タクシーアプリが浸透した将来は「乗りたいときに乗りたい場所で」がスタンダードになっていくかもしれません。当然、適した駅前タクシープールの在り方も変わってくるわけです。このように、時代のニーズに合わせて計画を変えることも私たちのミッションだと思っています。
榎本 計画変更による展望施設創出を通じ、社内では「計画はニーズに合わせて変えるべきだし、変えられる」というマインドが浸透しています。建築技術担当としては、時間的制約があるなかで決まった内容を変えるのは非常に厳しい話です。でも逆にいえば、常に渋谷にとってのベストを追求・実現できるよう、柔軟に変更できるだけの余地を持たせる臨み方が求められるのだと受け止めています。
――第Ⅱ期着工でゴールが見えてきましたが、そこに向けた想いは?
榎本 渋谷駅街区計画が目指すところは、開発を通じた街の価値向上で、超高層ビルなどの建物をつくること自体ではありません。つまり、渋谷の街について「こんな施設があったらいいよね」「あんな問題が解決されたらいいよね」というニーズありきなのです。このため、私自身は目先の事業収支より、末永く賑わいを育んでいくにはどうするべきかといった部分に時間と労力を割いています。根底にあるのは、渋谷の街が成長すれば、おのずと自社の成長につながるという長期的視点です。今後も、この軸は変えずに臨みたいですね。
石田 「『竣工』イコール『終わり』ではない」を強く意識し続けなければと思っています。建物や広場ができた後も、街の賑わい創出や課題解決に関わり続けるところに東急の存在意義があるからです。開発実務に従事するなかでは、たびたび複雑な問題や難易度の高い課題に直面するので、ともすれば目先の解決にとらわれがちです。しかし、私たちが担う本来的な役割は、長期的な視点から「街のあるべき姿」を考え実現していくこと。渋谷に進出してくださる企業や店舗、遊びに来てくださる方々、地元住民のみなさんなど、どなたにとっても「より良い街になった」と実感していただけるような進化を実現させていきたいと思っています。