
地酒や食材はもちろん、お皿や調味料まで群馬県産。 自称・世界一、群馬にこだわる居酒屋ナルカミ
- 取材・文:榎並紀行(やじろべえ)
- 写真:丹野雄二
- 編集:藤﨑竜介(CINRA)
Share

東急東横線の学芸大学駅を西口に出て、歩くこと約5分。商店街が終わるころ、都内在住の群馬県人らに愛される居酒屋・ナルカミにたどり着く。
お品書きには「桐生ソースかつ丼」や「上州ひもかわうどん」など、群馬にちなんだ料理がずらり。群馬県桐生市出身の店主・小野里全芳さんが腕を振るい、訪れる人の舌を楽しませる。
また店内を見回すと、群馬県のかたちをした特注の皿やオーナメントなど、さまざまな“群馬推し”アイテムが存在感を放つ。
高崎市出身の土屋翔平さんも、そんな郷土愛あふれるこの店に魅せられた常連の一人。20代前半だった初来店のときから、10年近く通い続けている。小野里さんを介して出会った同郷の仲間とのつながりや思い出も、大切な宝物だという。
「世界一、群馬県産の表示に敏感かも」と笑う店主のこだわりセレクト
――群馬県のかたちをした皿やオーナメントなど、店内のいたるところから群馬愛を感じます。
もう半分はネタみたいになっているけど、「どこまで群馬にこだわれるか」みたいなところはありますね。壁に飾っている“群馬オーナメント”は、彫金をやっている後輩がつくってくれました。日本酒の受け皿も群馬県のかたちだし、それに群馬の山の形状まで再現された皿もあるんです。 でこぼこしてるから、料理を盛りつけるスペースが限られるんだけど(笑)。
小野里
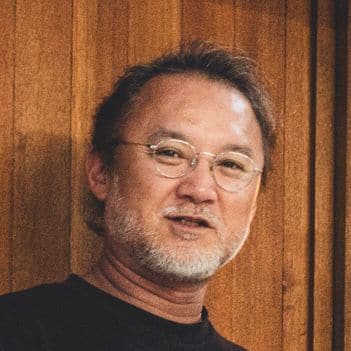



食材も酒も群馬産だし、あと烏龍茶は近所のスーパーで買うんだけど、製造元は群馬の会社ですよ。
小野里
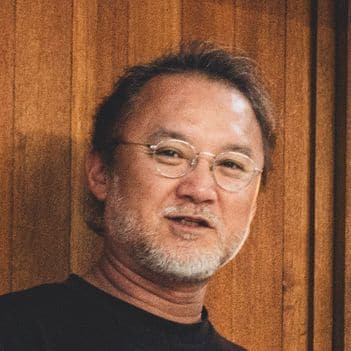
――徹底していますね。ちゃんとラベルを見て製造場所が群馬であることを確認してから買うんですか。
もう癖ですね。世界一、群馬県産の表示に敏感かもしれません(笑)。
小野里
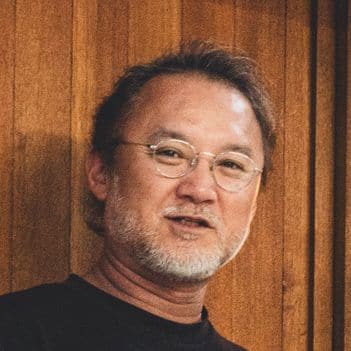

本当の群馬名物のほか、遊び心あふれる“名物風”メニューも
ナルカミほどひたすら群馬産にこだわる店は、地元の高崎にもないかもしれません。群馬の地酒��や野菜だけじゃなくて、醤油などの調味料まで地元産を使うくらい徹底しているのは、すごいと思います。
土屋

――土屋さんは20代前半のころから10年以上もナルカミに通っているということですが、きっかけを教えてください。
もともと職場の先輩が常連で、「東京におもしろい“群馬の店”がある」と聞いていました。それで、東京で用事があるときに、立ち寄ってみたのが最初です。 それ以来、東京で用事があるたびにここで飲むようになりました。とくに、3年ほど前からは仕事の都合で月2〜4回は東京へ来るので、来店頻度も増えていますね。
土屋


この店の魅力はまず、群馬うんぬんを抜きにしても料理がおいしいこと。��しかも、単においしいだけじゃなく、小野里さんならではのユニークさがある。群馬をおもしろく取り入れる絶妙なセンスに、いつも感心しています。 たとえば、メニューのなかには小野里さんの出身地である桐生の有名店の味をオマージュした「桐生ソースかつ丼」や「桐生系麻婆豆腐」などもあるのですが、そっくり真似るんじゃなくて、東京っぽく若干洗練された感じにアレンジしてあるんですよ。 そこに遊び心が感じられて、楽しい気分にさせてもらっています。
土屋


ちなみに、うちのメニューは「ソースかつ丼」や「ポテト焼そば」など本当の群馬名物もありますが、僕が勝手につくった“名物風”のメニューもあるんです。たとえば、「鮭の上州酒浸し」。いかにもご当地っぽい名前をつけているけど、こんな郷土料理は群馬にはなくて。
小野里
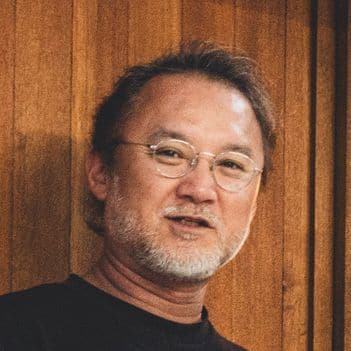
――え、ないんですか。
そうなんです。群馬って海がないから、保存のきく新巻鮭を食べる習慣があって、魚といったら鮭なんですよ。じゃあ、その鮭をどう提供しようかと考えて、海外の星つきレストランの調理法や、たまたま新潟に行ったときに見た鮭の食べ方を参考にしながら、レシピをつくりました。
小野里
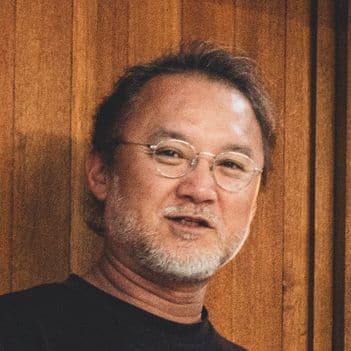
――だから“名物風”なんですね。
ええ。あとは、このナルカミ流「ピータン豆腐」も、オリジナルの名物風メニューです。台湾の台南市と群馬の前橋市は歴史的なつながりがあって、いまも良好な関係にあります。そこで、台湾のピータンと前橋に本社がある相模屋という豆腐メーカーの製品を合わせてみました。 「台湾と前橋のつながりを表す新名物」と、僕が勝手に言っています(笑)。
小野里
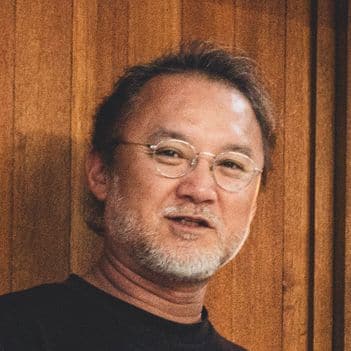

台風が来ても、群馬県人の絆で満席に
東京での仕事が終わると、ついナルカミへと足が向くという土屋さん。そこまで通い詰める理由は料理だけでなく、同郷の大先輩である小野里さんの存在が大きいという。カウンター越しの会話のほか、小野里さんを介したほかのお客さんとの交流も、土屋さんの人生を彩る大切な財産になっている。
――料理以外で、土屋さんがこの店に通い続ける理由はありますか。
やはり小野里さんの存在は大きいですね。小野里さんの仲間も楽しい人たちばかりで、この店自体がコミュニティになっています。小野里さんと話しているとわかると思いますが、本当にいろいろなことを知っていて、おそらく彼と話したいから足を運んでいる常連さんも多いんじゃないかと。 それに、小野里さんはお客さん同士をさりげなく会話でつなげるのも、うまいんです。
土屋

常連さんは、群馬から東京に出てきた人もいれば、他地域の出身者やずっと学芸大学にいる人もいます。この店でいろいろな交流が生まれるのは、楽しいですね。
小野里
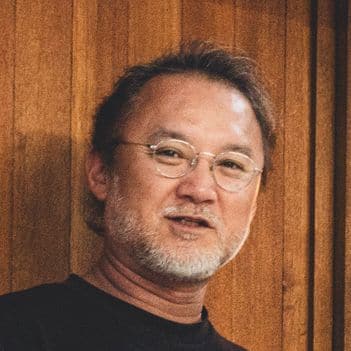

僕もこのカウンターでさまざまな人と出会って、仲良くさせてもらっています。たとえば、高崎出身の作曲家の吉田ゐさおさん(*)。ナルカミで初めて会って以来、何度も一緒に飲んでとてもお世話になっています。
土屋

* かつて音楽ユニット「Jungle Smile」の一員として活動。現在はプロデューサーとしてさまざまなアーティストの作品制作に携わるほか、CMや映画の音楽なども手がける
お客さん同士のつながりという意味では、個人的にはあのときも印象的なんだよね。ほら、数年前に台風直撃なのに群馬県人で店が満��席になった日。
小野里
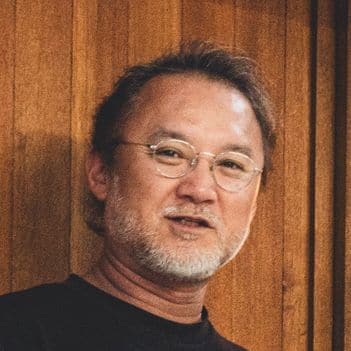
ありましたね。その日は僕も2泊3日で東京に滞在していて、どこかのタイミングで店に行くつもりでした。ただ、台風直撃の予報が出ていたのでさすがにやっていないかなと思って店のSNSを見たら、小野里さんが「台風で20人キャンセルが出た」と投稿していて。 じゃあ、行ってみようかなと。そしたら、なんと満席で。ものすごい雨のなか、常連の群馬県人が集まってきていたんです。
土屋

その日はたしか、大きな会社の群馬県人会の予約が入っていたんだけど、台風で会社が早上がりになって、さすがにそのまま飲みに行くのはまずいってことでキャンセルになったんですよ。それでSNSで何の気なしに投稿してみたら、常連さんたちがたくさん足を運んでくれて。 土屋さんもそうだし、この「群馬皿」をつくってくれた人も来てくれました。おもしろ半分みたいな気持ちもあったと思うけど、ありがたかったですね。
小野里
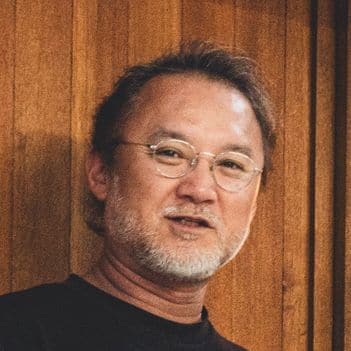
群馬、そしてナルカミを特徴づける「かんます」の文化
出身地であるというだけで、ここまでの群馬愛が生まれるものなのか。そう小野里さんに問うと、「じつは群馬に住んでいたころは、それほど愛着を感じていなかった」という意外な答えが。小野里さんの地元への思いは、いつ、どんなきっかけで膨らんでいったのか。また、小野里さんと土屋さんは、群馬のどんなところに魅力を感じているのだろうか。
――群馬県出身であること以外に、小野里さんがここまで群馬を推す理由は何なのでしょうか。
僕は若いころ、スコットランドに住んでいた時期があるんです。当時、現地の友人と会話していて感じたのは「世界史って、ほぼヨーロッパの歴史なんだな」ということ。日本人は義務教育で西洋史も習うから、ヨーロッパの歴史的背景は何となくインプットされているじゃないですか。 でも、逆にヨーロッパの人の多くは日本のことをほとんど知らなくて。そこに、若干のはがゆさを覚えました。
小野里
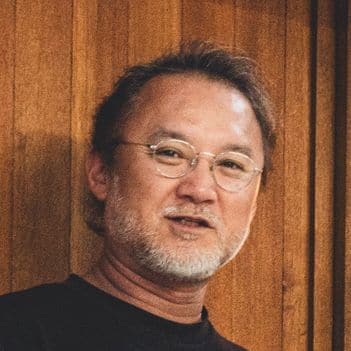

それと同時に、「はたして、自分自身も日本のことをちゃんと知っているのか」という問いも浮かんできて。もっと、ちゃんと自国のことを理解したい、魅力を知りたいと考えていたら、最終的には自分のルーツである群馬にたどり着きました。 じゃあ、自分のルーツをどう表現していこうかと模索していった結果、気づけばこんな店をやっていた。まさか、こんなに長くやるとは思いませんでしたけどね。
小野里
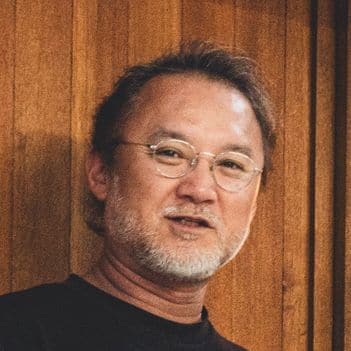

――あらためてですが、群馬の魅力とは。
いろいろありますが、やはり歴史と食文化ですね。たとえば、桐生名物のポテト焼そばって、戦時中から食べられていたメニューなんですよ。 当時は食料が限られたので、手に入るもので子どもにお腹いっぱい食べさせるため、保存のきくソースやじゃがいもともやしなどを組み合わせた「子ども洋食」というおやつが生まれました。それに蒸し麺を加えたものが、ポテト焼そばのルーツといわれています。
小野里
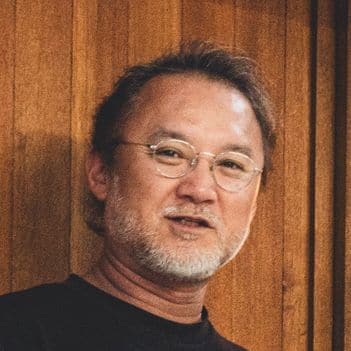
――当時の状況だからこそ、生まれた料理なんですね。
そう。それからソースかつ丼も、もともとは桐生の機織りの女工さんたちに精をつけてもらおうと考案されたものです。本当はうなぎを食べさせたいけど、希少品なので難しい。そこで、近隣のソース工場のソースにうな丼で使うようなタレを混ぜて、それにカツをくぐらせてご飯にのせたのがはじまりとされています。 こんなふうに、知れば知るほどおもしろい話がたくさんあるんですよ。
小野里
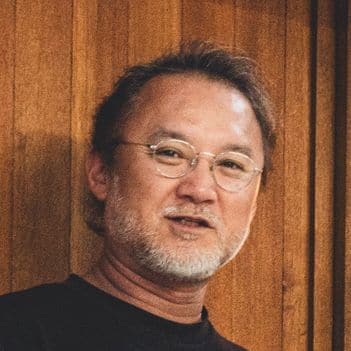
こういう話を聞けるのも、ナルカミの良さなんですよね。僕自身も店に通うようになってから、より群馬のことを知るようになって、地元への愛着が増しました。
土屋

――土屋さんは、群馬のどんなところが魅力だと感じますか。
群馬弁で「かんます」という言葉があります。「かき混ぜる・かき回す」という意味ですが、群馬って昔からさまざまな人や文化を受け入れて、それらと混ざることで発展してきた側面があるんです。 江戸時代の上州(群馬)には、中山道や三国街道から多くの人がやってきていました。そういった外との交流のなかで生まれていった独特な文化が、一番の魅力なのかなと。 この店もそうじゃないですか。小野里さんが各地の名物などをうまく取り入れながら、群馬のものと混ぜて素敵な料理に昇華している。 そういう意味では、ナルカミは群馬の良さを体現している店なのかもしれないですね。
土屋


群馬文化にどっぷり浸ることができる居酒屋、ナルカミ。同郷人だけでなく、他地域の出身者も受け入れ、群馬の料理や酒を通じて縁を育む。外部との交流で発展してきた群馬を象徴するような、懐の深さが魅力だ。
そんなナルカミが店を構える、学芸大学。「落ち着き�と品を感じる街で、いい意味で突拍子もない人がいない。一番突拍子もないのは、こんなところでなぜか群馬の店をやっている僕でしょうね」と小野里さんは笑う。
この街特有の穏やかな雰囲気のなか、ナルカミはこれからも、群馬文化の発信地として異彩を放つ。

Share





